|
◆新刊「傾聴は難しい」と感じているあなたへ(電子書籍) https://amzn.to/43dJMtQ ◆カウンセリング面談(5/23) ◆5月24~25日 初心者のための記憶法講座 |
■無料プレゼント■
『楽に聴ける聴き上手』を目指す人の間で、
絶対に、一度は受講しておかないと...
と言われている 『傾聴サポーター養成講座』の秘密を、動画でプレゼント中!!
今すぐ、LINEに登録してプレゼントを手にしてください!
友だち登録はこちら
https://jkda.hp.peraichi.com/seminar-2409
──────────────────
傾聴サポーター養成講座 随時受付中
オンライン体験会&説明会(オンライン)
・5月29日(木)19:30
・6月8日(日)19:30
・6月21日(土)19:30
・6月22日(日)10:00
時間 120分
※質問タイムあり
定員 4名 読者価格 ¥4,000→¥2,000 ※50%OFF
申し込む→ https://x.gd/aqsb5
─────────────────
いつもありがとうございます。
心の中でよく返事をする、岩松正史です。
不登校の子どもにどう接すればよいのか、
悩んでいる保護者の方は少なくありません。
無理に学校へ行かせるのも逆効果。
かといって、
放っておくのも心配になります。
今回は、不登校の子に向き合ううえで
大切にしたい6つのポイントをご紹介します。
親のセルフケアや会話のヒントも
あわせてお伝えします。
------------
1.家を安全地帯にする
------------
家が子どもにとっての安全基地になります。
親の足音がするだけで、子どもが
ドキッとするよう関係だと
危険地帯になってしまいます。
責めず、比べず、ただそばにいと。
「あなたがいてくれれば嬉しい」が
伝わるるだけで安心感につながります。
------------
2.気持ちにアプローチする
------------
「なんで行かないの?」より、まず
「どう接していたら安心かな」
安心感にアプローチしてみてください。
また、いまは特に何もないといわれたときは
「出来ることは何でもするから、声かけてね」、
と伝えて、そっと見守ることも支援です。
------------
3.今の状態を否定しない
------------
休んでいる時間にも意味があります。
「いまは行けそうにない気持ちなんだ」
そんなふうに気持ちを捉えることで
子どもも自分を否定しにくくなります。
------------
4.生活リズムを整えるサポート
------------
朝起きられないこともあります。
日光を浴びる、朝食を一緒に食べるなど
少しずつリズムを整える工夫をしましょう。
約束帳を作ってタスク化して
チェックさせていく仕事場の様な
雰囲気にならないようにしましょう。
------------
5.学校以外の道も視野に入れる
------------
フリースクールや通信学習など
学びの形はひとつではありません。
最近ではオンライン教材を学校が
提供していたりもします。
いきなり安心で居心地のよい場所を
作ろうとせず、部分的に安心感や
やる気が満たせる部分を1つずつ
探していきましょう。
「何かやってみたいこととか、
いまできずにいることで
不安に思ってることはない?」
と訊きながら、不安や安心の
想像をしてもらい選択肢を広げてください。
------------
6.親が自分の心も同時にケアする
------------
子どもを支えるには、
親の心の安定がなにより大切です。
子どもがよい方向に変わらなければ
親がいつも機嫌が悪いのであれば
それは、親の感情の責任を子供に
押し付ける依存状態になってしまいます。
日頃から信頼できる人に少し話す。
部分的に話せる人を、何人か持っている
事が大切です。
また、
「怒らないようする努力」ではなく
「怒った自分を許す努力の方」をしたほうが、
怒りとうまく付き合えるようになります。
一気に問題をすべて解決できるような
相談窓口はなかなかありませんが、
プライベートな知人だけでなく
相談機関の窓口などは、負担を
部分的に軽減できる場としても有効です。
人に話していることで、ときどき
有効な発見もあったりします。
不登校の問題は、学校に行くか行かないかという
見かけの問題ではなく、
子どものことで困っている親と、
学校に行けないことで困っている子供という
2人の困っている人がいる状態です。
話せたり、わかってくれていたり
見守ってくれたりといった風に
「安心な関係」があることが一番の支援になります。
長く続く可能性もあることなので
結果に一喜一憂せず、子ども自身が
喜びを感じられた時は、一緒に喜びを
共有するくらいの気持ちで過ごしましょう。
|
◆傾聴1日講座 ・東京 5/12、6/2、6/28、7/7、8/4、8/30、9/8、10/6、10/25、11/10、12/1、12/27 ・大阪 5/12、5/24、6/8、6/18、7/5、7/26、8/2、9/1、9/24、10/6、10/18、11/8、11/12、12/2、12/7 ・オンライン 5/12、5/19、6/18 https://jkda.or.jp/keicho_oneday_lecture ◆傾聴サポ-タ-養成講座 |
<編集後記>
お店に行くとよく
「いらっしゃいませ!」
と、元気よく声をかけられることありますよね。
そんなとき、私はいつも
(いらっしゃいました!)
と心の中で返事をしています。
似たようなことが、
車を運転するときにもあります。
うちの車は、エンジンをかけると
「ETCカードが挿入されていません」
といつも行ってきます。
なので、
(ETCカードは、挿入していません)
と、心の中で返事毎回しています。
いかがでしょうか?
あなたは、心の中でいつもしてしまう
返事は何かありますか?
今日もいい一日をお過ごしください!
◆傾聴関連◆
・傾聴1日講座(基礎)
・傾聴サポーター養成講座


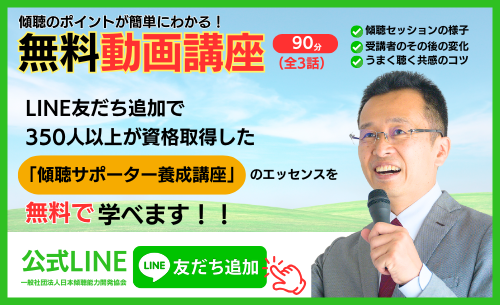
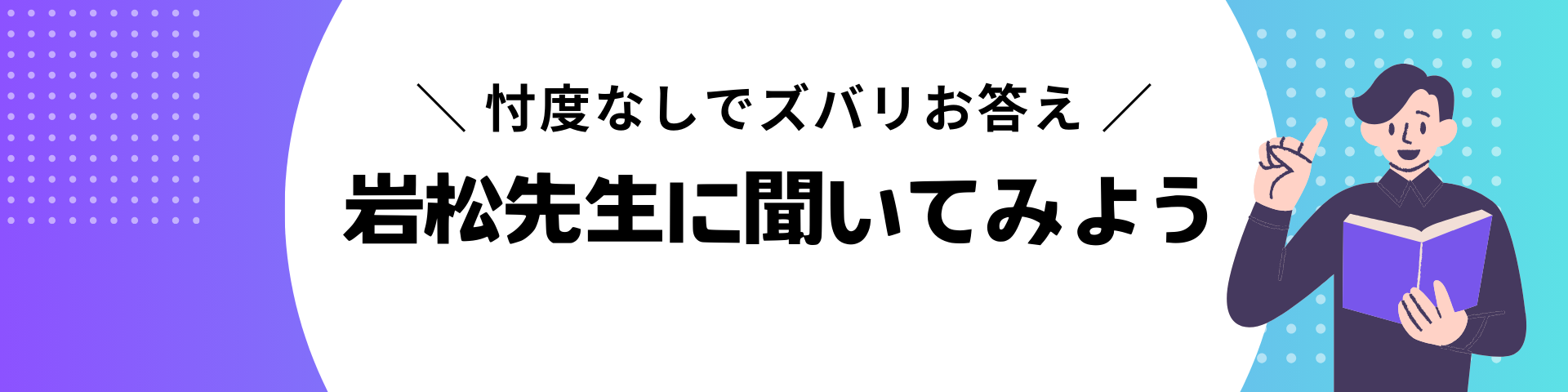
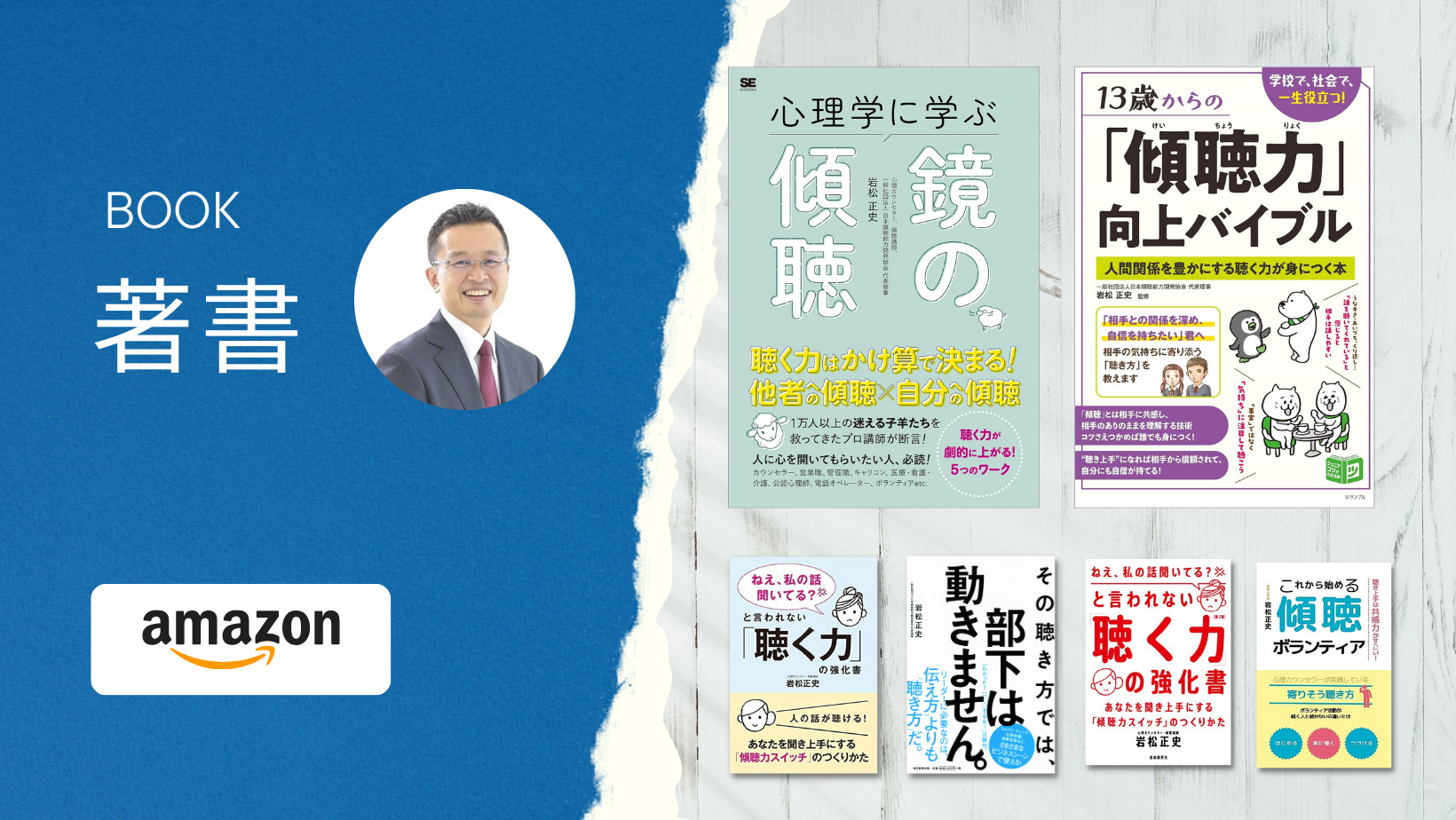
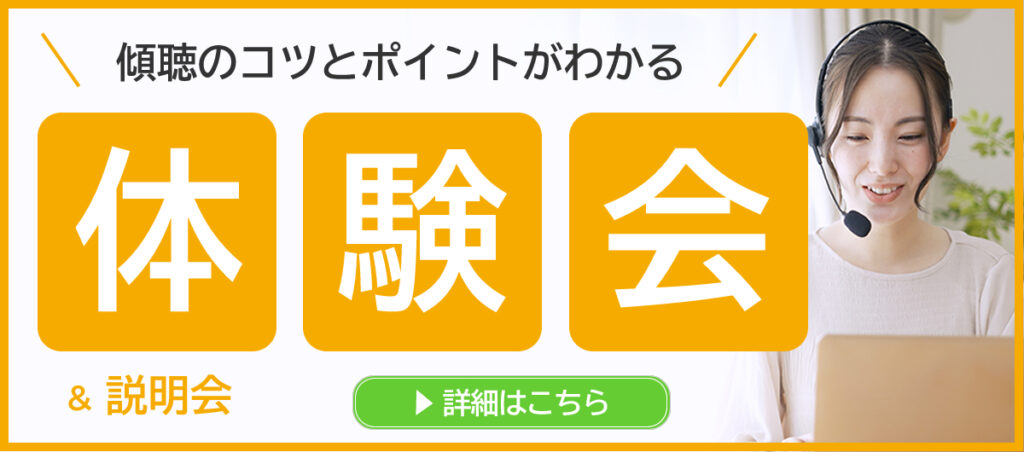

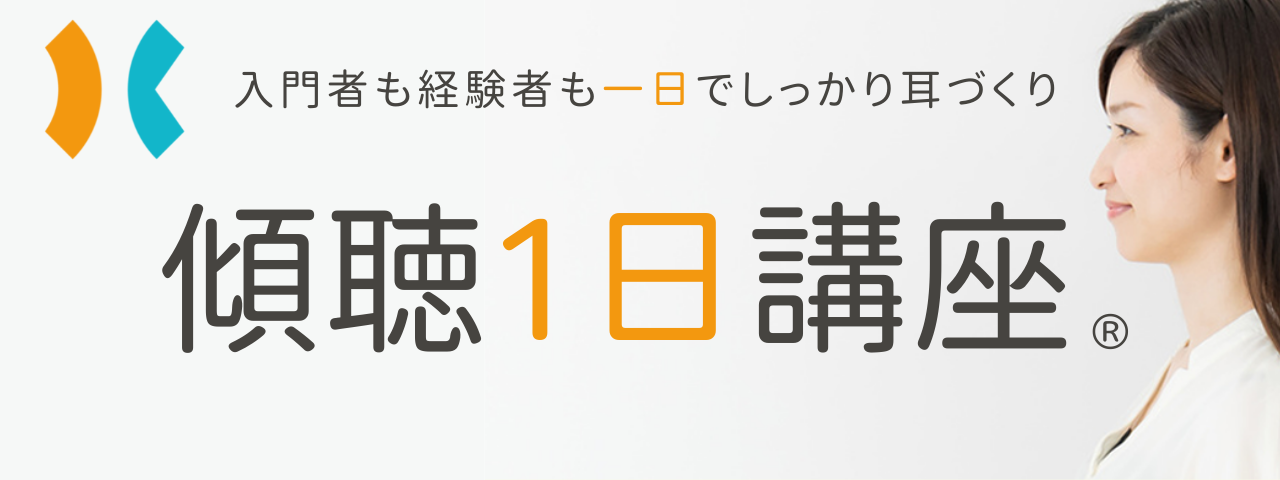




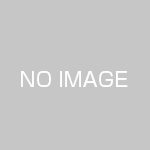

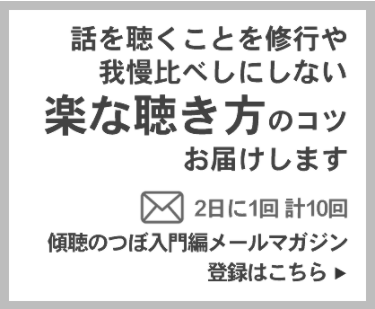
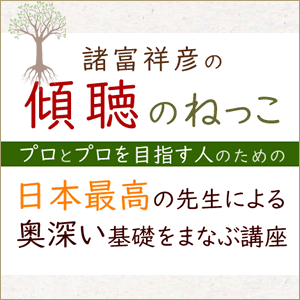
 PAGE TOP
PAGE TOP