|
【募集】協会設立10周年記念ワークショップ テーマ「新時代の傾聴」 ~傾聴学びはじめ、学びなおし~ 日程:9月20、21日 10~17時 会場:国立オリンピック記念青少年総合センター(東京、代々木) 参加費:1日8000円、2日15000円 定員:60名 ※変更になりました 1日目 30名→残り8名 2日目 30名→残り10名 詳細→https://self-keicho.com/10th ※1日のみ参加も可 |
■無料プレゼント■
『楽に聴ける聴き上手』を目指す人の間で、
絶対に、一度は受講しておかないと...
と言われている 『傾聴サポーター養成講座』の秘密を、動画でプレゼント中!!
今すぐ、LINEに登録してプレゼントを手にしてください!
友だち登録はこちら
https://jkda.hp.peraichi.com/seminar-2409
──────────────────
傾聴サポーター養成講座 随時受付中
オンライン体験会&説明会
・9月4日(木)19:30
・9月15日(月祝)10:00
・9月27日(土)19:30
・10月2日(木)19:30
・10月12日(日)19:30
・10月18日(土)19:30
・10月19日(日)10:00
時間 120分
※質問タイムあり
定員 4名 読者価格 ¥4,000→¥2,000 ※50%OFF
申し込む→ https://x.gd/aqsb5
─────────────────
いつもありがとうございます。
味噌汁もごはんも左にして欲しい、岩松正史です。
今週、とても嬉しい出来事がありました。
4年間、ボイトレではじめての
劇的変化が起きたんです。
歌を上手くなりたい人がの多くが
目指すのは「ミックスボイス」です。
ミックスボイスとは、高音も低音も
無理なく、自由に出せる発声法です。
これができれば、どんな歌も
なめらかに歌えるという、
歌う人にとっての夢の境地です。
そのために、レッスンにいくと
必ず最初に「ハミング」をやります。
口を閉じて「フフフ~」と
鼻に響かせる、あの練習です。
「ミックスボイスにはハミングが大事」
と言われつづけ、信じてずっと続けてきました。
ですが、
正直なところ、その関係性が
いまいち実感できないまま、
ただ適当にやっていました。
ところが、
数日前、カラオケで1人練習していたときに、
突然その瞬間が訪れたのです。
今まで力を込めても引っかかったり、
抜けたりして出なかった音が、
嘘みたいに自然につながって出てきます。
その時、「これがミックスボイスか!」と
からだが本当に理解した感じがしました。
4年間探し続けていた感覚に出会えたことに感動して、
52歳のオジサンは、カラオケボックスで
勝手に独りで目頭があつくなっていました。
(ちょっと、気持ち悪い光景ですが(汗))
そして、出来るようになったその
ミックスボイスの感覚を言葉にするなら
やっぱり・・・
「ハミング」なんですよね(汗)
でも、今まで自分がやっていた
ハミングとは別物です。
つまり、ハミングにも種類があって
いままでの私は、ミックスボイスとは
関係ないハミングをしていたんですね。
それは、ミックスボイスが出来るようになって
初めて区別がわかるようになりました。
この気づきは、傾聴にも重なります。
ロジャーズは、一致・受容・共感が
傾聴成功の鍵だと強調しました。
でも、
それは完成系の状態を言っているだけで
どうすれば実現できるのか?
具体的な方法は示されなかったことで
多くの批判も受けました。
でも、その理由が今はわかります。
どの様に発声するハミングが、
ミックスボイスにつながるハミングなのか、
感覚は伝えようがないからです。
ロジャーズが言っていることは、
「ミックスボイスができる人は、いいハミングができる」
と言っているのと同じなんですよね。
傾聴を学ぶ人は最初、手探りで
教わった型を真似することから
始めるのが一般的です。
でも、その型そのものを身につけようとすると
多くの場合、路頭に迷うことになります。
なぜなら、
正解の感覚がわからない人は
その型への取り組み方そのものが
ズレている可能性が高いからです。
だから、
大切なのは自分がいま理解している
型そのものを身につけようとすることよりも、
こんなハミングもできかな?
あんなハミングもあるかな?
と、型を試行錯誤して研究する姿勢です。
試行錯誤そのものを愉しんでいると
突然「これだ!」という感覚が
不意に訪れたりします。
それは確かにいつ来るかわかりませんが、
「型」から外れた努力をしてなければ
確率的に訪れやすいことは間違いありません。
つまり、
うまい、下手の結果が大事なのではなくて、
「試行錯誤そのもの」で実力がつくわけです。
|
◆傾聴1日講座 ・東京 8/30、9/8、10/6、10/25、11/10、12/1、12/27 ・大阪 9/1、9/24、10/6、10/18、11/8、11/12、12/2、12/7 ・オンライン 8/5、8/25、9/14、9/29、10/12 https://jkda.or.jp/keicho_oneday_lecture ◆傾聴サポ-タ-養成講座 |
<編集後記>
和食の定食屋さんに行くと、
いつも納得できないのでは
お膳の上に味噌汁を置く位置です。
たいてい、
白米は左、みそ汁は右に置かれています。
でも、みそ汁食べるときお椀は
左手で持つので、とりにくくて仕方ありません。
茶碗もお椀も左手で持つので、
2つとも左側において欲しいものです。
歴史的に左上右下という
思想があるのはわかりますよ。
でも、それってこの時代に
日常生活で必要?って思います。
なので、私は、最初に味噌汁を左に
配置し直してから食べ始めます。
過去から続いている習慣て
現代では意味がないもの多いですよね。
伝統も大事かもしれないし
効率がすべてじゃないかもしれませんけど
「いま本当にそれ必要?」って
考えることも必要だと思うんですよね。
今日もいい一日をお過ごしください!

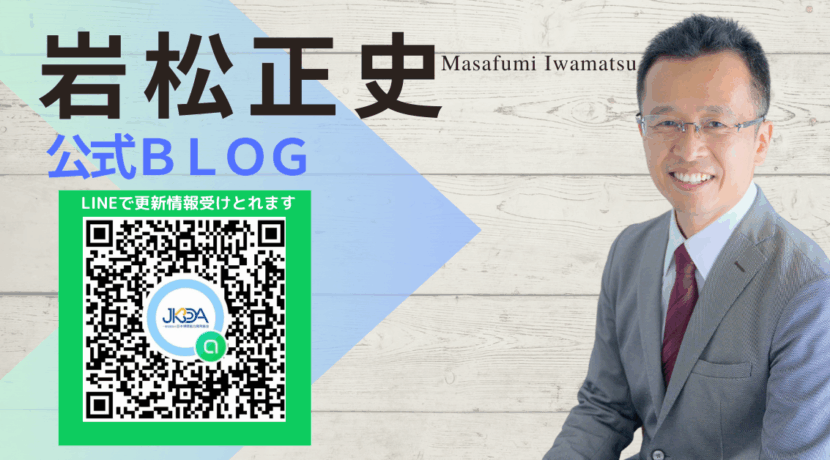
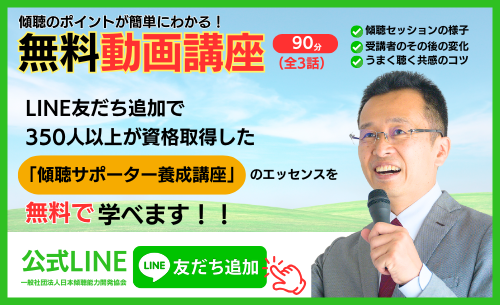
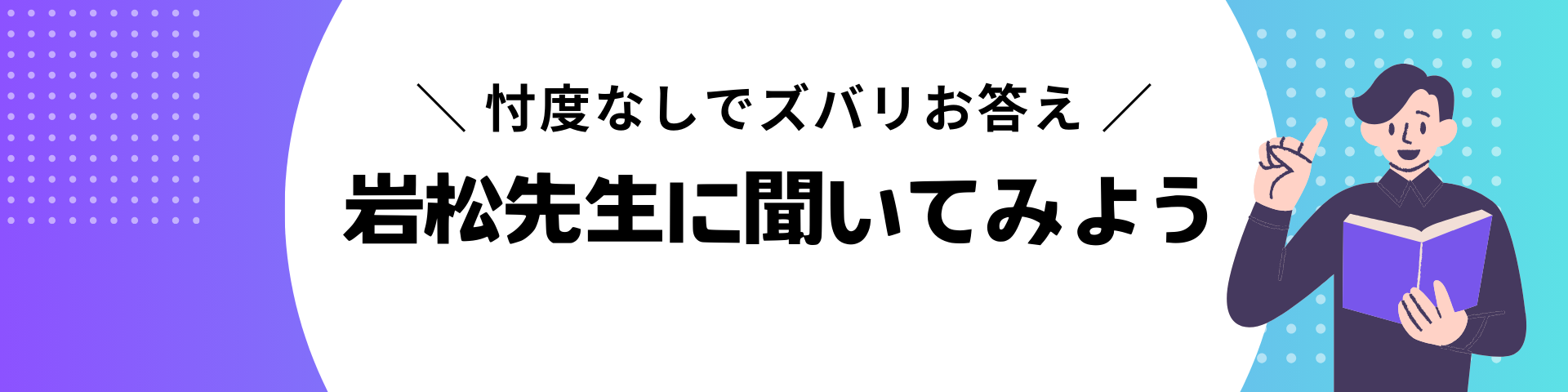
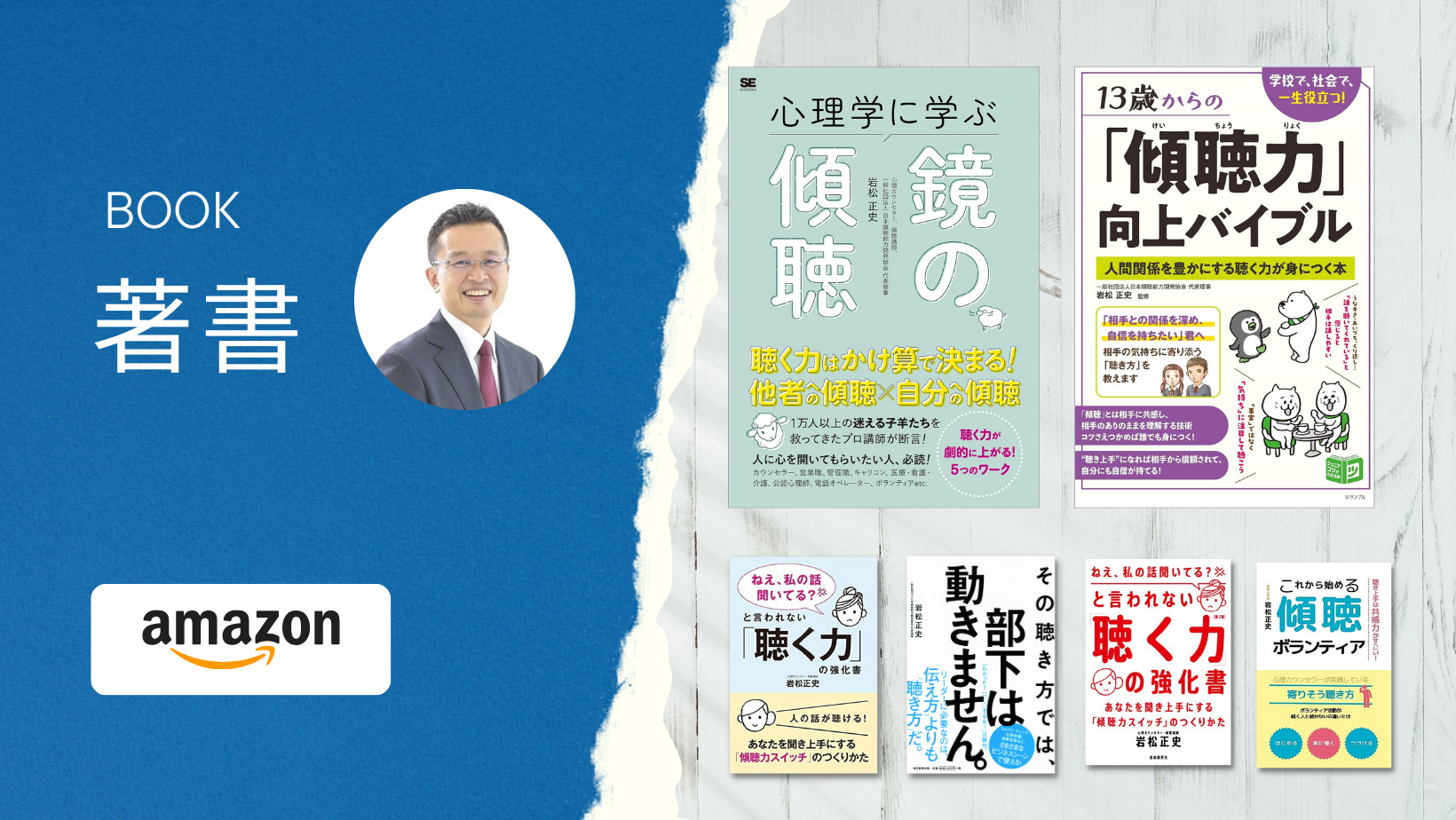
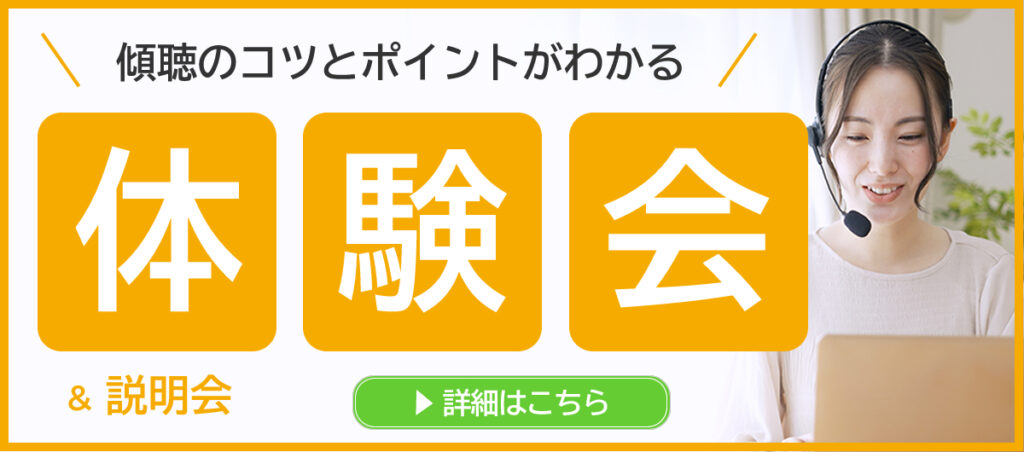

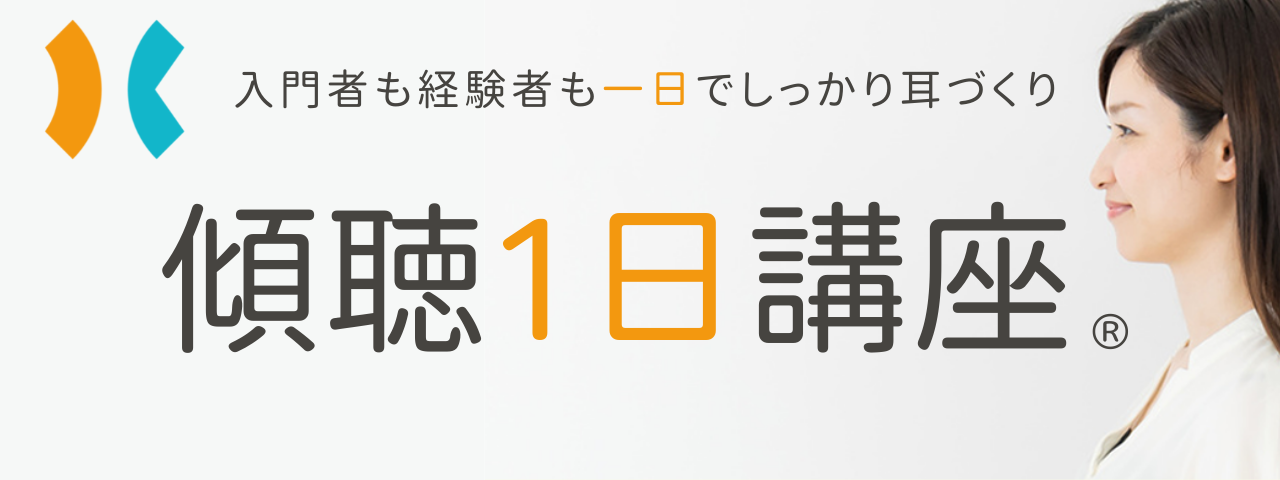




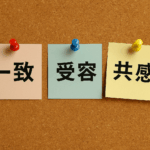
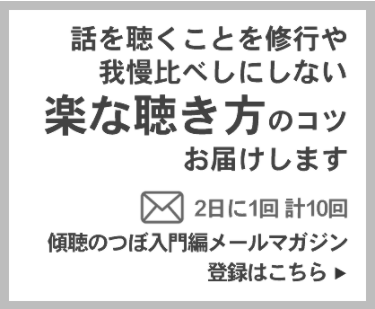
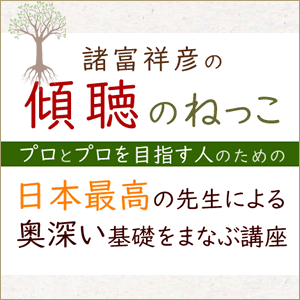
 PAGE TOP
PAGE TOP